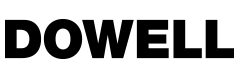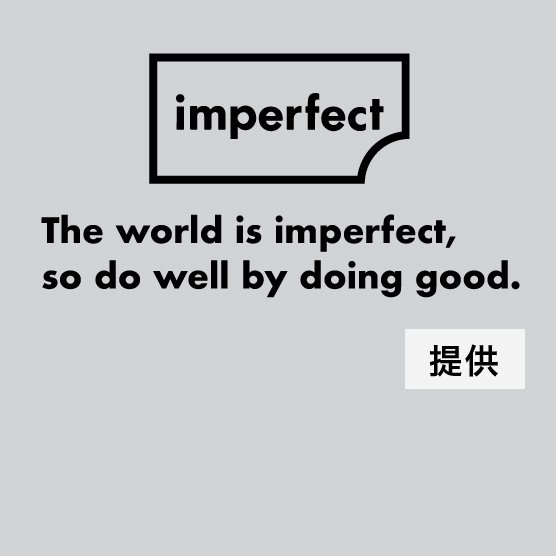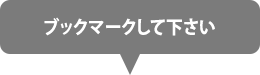コショウの病気が、アグロフォレストリー農法への転機に
DOWELL編集部: ところで、トメアスーでアグロフォレストリー農法が採用されたのは理由があるのでしょうか。
佐久間さん: 理解しやすいように、トメアスーの歴史と合わせてお話しますね。実はここは、1929年頃、日本政府の移民政策で大勢の日本人が移り住んだところなんです。今でこそかなり大きな町ですが、当時は小さな町がぽつんとあるという状況で、アマゾンの原生林を切り拓くところからのスタートだったと聞いています。
当初はカカオも育てていたんですが、1950年頃にコショウの価格が高騰し、農家はこぞってコショウをつくるようになり、他の作物は一切手がけなくなったそうです。でも1960年代にコショウの病気が流行った結果、コショウが全滅。収入がゼロになってしまったんです。畑のコショウが全て駄目になっていくのを目の当たりにした日系人の農家は、単一栽培の怖さを学びました。この教訓を生かそうと複数の作物を組み合わせて栽培するようになったと伺いました。
DOWELL編集部: この複数栽培がアグロフォレストリー農法へと発展していったのですね。カカオの若木は強い日差しから守る必要があり、そのために日傘の役割を果たすシェードツリー(日陰樹)が必要だそうですね。こうした樹木も育てていたのですか?
佐久間さん: そのシェードツリーのありようが、トメアスーのアグロフォレストリー農法の大きな特徴なんです。一般的にシェードツリーは日陰をつくるための存在と思われていますが、トメアスーでは、シェードツリーも収入をもたらすんですよ。バナナやコショウだったり、もっと背が高い樹木だと、ヤシ科のアサイーやブラジルナッツだったり……。その実を収穫して収入を得られるものばかりなので、無駄がなく経済的に優れているんです。
例えばアフリカでもアグロフォレストリー農法は盛んですが、元々ある森をベースにしていて、後から植えた作物のみで収入を得ています。逆に言うと、元からあった森からは何も得られません。でもトメアスーの場合は、アマゾンの伐採地で荒廃地だった土地を整えるところから始まっていますから、植物を計画的に選べます。高い木も低い木も収入がある作物で構成することができるんです。そして最終的には、荒廃地だった場所がまるで森のようになるんです。
更に時間軸で見れば、コショウやバナナは1~2年目で収入が得られます。カカオは3~5年掛かるので、それまではカカオ以外の作物で生計を立てられるように設計しているんです。
DOWELL編集部: そこまで緻密に計算されているんですね。
森の中でつくるアグロフォレストリー農法は、実は緻密な計算の上で成り立っている農法。
後編では、その特徴を更に掘り下げてお話を伺います。
(後編に続く)