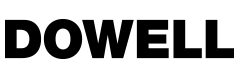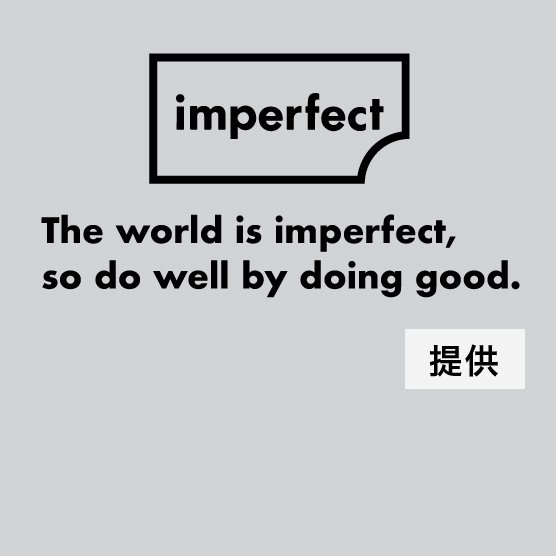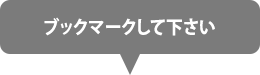音楽との出会い、アンジーとの出会い
DOWELL編集部: 現在は“サムライギタリスト”と呼ばれ、世界で活躍するMIYAVIさんですが、子どものころはサッカー選手を目指していたんですよね。
MIYAVIさん: セレッソ大阪のジュニアユースに在籍していて、プロを目指していました。朝から日が暮れるまでボールを追いかけていましたが、14歳の時に足を怪我してしまい、サッカー選手への道を断念せざるを得なくなったのです。
心にぽっかり空いた穴を埋めてくれたのが、たまたま手に取ったギターでした。すぐに夢中になり、それこそ寝る間も惜しんで弾いていました。サッカーがそうだったように、ギターも、型にはまることなく自由に自分自身を表現できるところが魅力で、すぐにのめり込んでいきました。
DOWELL編集部: ミュージシャンには、誰かに憧れて、その演奏を真似ることから始めたという方が少なくないようですが、MIYAVIさんは違ったのですね。
MIYAVIさん: もちろん沢山のアーティストから影響は受けましたが、「誰かになりたい」ということはなかったですね。最初はコードとかも分からず、まったくデタラメに弾いていました。それでも音楽を創るという喜びを感じられて、その思いは今も同じです。これがあれば自分が自分らしく生きることができる、そう確信できたんです。
DOWELL編集部: いまでは、ピックを使わない“スラップ奏法”という独自のスタイルが、MIYAVIさんの代名詞です。
MIYAVIさん: テクニック的には、ラリー・グラハムさん、マーカス・ミラーさん、ルイス・ジョンソンさんのような、チョッパーベーシストと呼ばれる先達の演奏を見て学びました。でも、スタンスとしては日本の伝統楽器である三味線のような音を西洋の楽器でも鳴らしたいという思いがあり、それが現在のスラップ奏法につながっています。
まずは自分らしくありたい。だから自分との向き合い方を何より大切にしてきました。それは音楽に限らず、すべてにおいてです。現在は周りの人や、溢れんばかりの情報のアップデートに着いていくことが求められがちですが、まず個の部分がしっかりしていないと、発展や広がりはないと考えます。
DOWELL編集部: その音楽に魅かれたアンジェリーナ・ジョリーさんが、自身が監督した映画『不屈の男 アンブロークン』(アメリカ/2014年)で、MIYAVIさんに出演をオファーされたんですよね。第二次世界大戦中の日本軍の捕虜収容所で、主人公のアメリカ人に辛く接する所長を演じられたとか。大変センシティブな役柄だったと察しますが、どのような思いで引き受けたのでしょうか?
MIYAVIさん: 役者をするのが初めてということ、そして製作前から反日的な作品ではないかと話題になっていたことで、正直、自分の音楽家としてのキャリアに影を落とすのではないかと、とても悩みましたね。でも、監督としてのアンジー(アンジェリーナ・ジョリーさんの愛称)の作品への思いを聞いて、出演することを決めました。
この作品は、日本とアメリカが戦争で勝ったとか負けたとかいう話ではなく、ひとりの不屈の男の物語です。「自分を苦しめた人たちを最終的には許すという境地。その境地に達する強さを描きたい」と言われて、それはグローバルなメッセージだと思いました。アメリカ人だけでなく日本人も学べる映画だと。この物語の主人公が放つ光を、より際立たせる影として僕が必要とされるなら、この作品のためにがんばってみようと考えたのです。
DOWELL編集部: この出会いがきっかけで、アンジェリーナ・ジョリーさんが特使を務める国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の活動に参加するようになったのですね。
MIYAVIさん: アンジーとは、撮影期間中にいろいろな話をしました。本当に強い女性で、常に子どもたちや弱者のために戦っている。彼女から難民のことを知り、その支援活動をしているUNHCRの存在も知りました。いつしか「僕にも何かできることはないだろうか」と考えるようになっていました。彼女が新たなドアを開いてくれました。