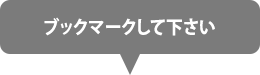日本の子どもたちから履けなくなった中古のシューズを回収し、アフリカ・ケニアなどの途上国で、裸足や裸足に近い状態の生活を余儀なくされている子どもたちへ贈り続けてきた『スマイル アフリカ プロジェクト』。このプロジェクトの立ち上げから尽力されてきたのが、シドニー五輪女子マラソンの金メダリスト・高橋尚子さん。笑顔が素敵な“Qちゃん”が、たくさんの子どもたちに“笑顔”を届け続けてきたお話を伺いました。

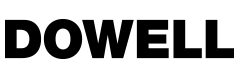

日本の子どもたちから履けなくなった中古のシューズを回収し、アフリカ・ケニアなどの途上国で、裸足や裸足に近い状態の生活を余儀なくされている子どもたちへ贈り続けてきた『スマイル アフリカ プロジェクト』。このプロジェクトの立ち上げから尽力されてきたのが、シドニー五輪女子マラソンの金メダリスト・高橋尚子さん。笑顔が素敵な“Qちゃん”が、たくさんの子どもたちに“笑顔”を届け続けてきたお話を伺いました。
DOWELL編集部: 足が大きくなって履けなくなってしまった日本の子どもたちのシューズを、裸足やビーチサンダルで生活しているアフリカの子どもたちに届ける『スマイル アフリカ プロジェクト』。2009年に始まり、昨年11月に目標の10万足に達するまでの11年間、毎年現地に赴くなど継続的に携わってきた高橋さんですが、どのようにしてこのプロジェクトが立ち上がったのか、その経緯から教えていただけますか。
高橋さん: 2008年に現役を引退したとき、「アフリカのケニアでマラソン大会をやりませんか?」と誘われたことがきっかけです。せっかくケニアに行くのだから、何か私たちにできることはないだろうかと模索したとき、ランナーにとって体の一部であり、一緒に走ってくれるパートナーでもあるシューズを活用できないものかと考えました。
そこでケニアの子どもたちの靴事情をリサーチしてみたら、靴を履けない子どもたちがいて、そんな子どもたちは、足の傷から寄生虫や菌が入り破傷風などの感染症を患い、命を落としてしまうこともあるということを初めて知ったのです。ならば成長によって、まだ使えるのに下駄箱で眠っている日本の子どもたちのシューズを現地へ届けられないかと。この構想が実を結んだのが、『スマイル アフリカ プロジェクト』です。

DOWELL編集部: 2009年に初めてシューズを持って現地を訪れたとき、どのような感想を持たれましたか? 現地の子どもたちの反応はいかがでしたか?
高橋さん: ケニアに着いて最初に訪れたのは、キベラという大きなスラムでした。首都ナイロビとの間を遮る壁や境界線となる門などは存在しないのですが、近づいていくにつれ非常に隔離されているところなんだなと悟って。現地に行くまでは、「初めてシューズを履いた子どもたちは、きっと羽が生えたように飛び回って喜んでくれるんだろうな」と明るい想像ばかりしていたんですけど、そんな甘い考えはすぐに砕かれました。
さらに歩を進めると、異臭が漂い始めてきました。スラムに入ると5㎝ほどのゴミの層が道路を覆っています。道路といっても真っすぐでなく、くねった田んぼのあぜ道のようなもので、ガサガサとゴミを踏みしめるようにして歩くしかないんです。雨上がりは特に酷く、ドロドロにぬかるんでいて、つるっと滑ることもあります。ゴミの中にはガラスの破片などに加えて、動物や人間の糞尿も混ざっているのですが、そこを通らざるを得ません。歩くのに苦戦しているとその傍らを子どもたちが、裸足やビーチサンダルですり抜けていくんですよ。
キベラでまず足を運んだのが病院でした。子どもたちが常に7~8人いるのですが、みんな申し合わせたように小さな傷を足に負っていました。この傷に寄生虫がついたりバイ菌が入ると、膿んだりして足を切断してしまうこともあるというんです。でも、靴さえあれば助かります。「靴は歩くための道具である以前に、命を守る防具なんだ」と気づかされた瞬間でした。
DOWELL編集部: それまでの常識が崩されてしまったんですね。
高橋さん: はい、ガラガラと音を立てて……。これまで靴のない世界というのが、全く自分の中でイメージができていませんでした。靴がない生活がどれほど大変で危険かということを思い知って愕然としましたね。
でも落ち込むことだけでなく、よいこともありました。学校で、子どもたち一人ひとりにサイズの合ったシューズを選んで履かせていくと、みんな履いた瞬間から笑顔になって校庭や学校の周囲をくるくると走り回るんですよ。そのこぼれるような笑顔を見たとき、来てよかったという思いと支援してくれた人たちへの感謝の念がこみあげてきましたね。

DOWELL編集部: ショッキングなことが多かったようですが、シューズは無事に届けられたのですね。
高橋さん: JICA(独立行政法人国際協力機構)(※注)や青年海外協力隊のみなさんのアシストもあって何とか。車で目的地までは行けないので、最後はシューズを詰めた段ボールを担いで歩かなければならなかったのですが、治安も悪いため、警察や地元の人々とコミュニケーションを取りながら、運びました。シューズだけ置いていったのでは、誰かに横取りされてしまう可能性がありましたから。子どもたちに履かせるところまでやらないと届けられないというのが、悲しいですがキベラの現実でした。
DOWELL編集部: 時間の経過とともに、状況は変わっていったのでしょうか。
高橋さん: それが私たちの予想以上に、劇的に変わっていったんですよ。
1年目に訪れた2,000名が通う学校で、陸上選手になりたいと言った子は、モーリスという少年ひとりでした。なんでなりたいの? って尋ねたら、「僕には家族がいる。でも世の中にはストリートチルドレンや親がいない子どももたくさんいるから、そんな子どもたちの役に立ちたい。だからスターである陸上選手になりたいんだ」って言うんです。まだ小学2年生ですよ。
彼の家にお邪魔したとき、テーブルを置いたらいっぱいになるような4畳ほどの部屋に案内されて、「モーリスの部屋?」と聞くと、驚いた表情で、家族みんなでここに住んでいると。(やってしまった)と後悔すると同時に、こんな境遇にいる子どもが、他の子どもたちのことを思いやれるってすごいなと感動してしまいましたね。
そして2年目。新たな学校や施設に配ることをしつつ、もう一方で、プロジェクトに参加してくれている皆さんの靴がどのように使われているかを報告するために、キベラを再訪もしました。そこでモーリスと再会。彼のシューズは親指や中指のところに穴が開いて、真っ黒になっていました。それを見ていたら、「ナオコごめんね。毎日走っているから、一生懸命洗ったんだけど、こんなにボロボロになっちゃった」って謝るんです。
でも私の受け取り方は違いました。日本ではほぼ不用品だったシューズが、こんなに使えるなんてと驚いたんです。もしかしたらとっくに捨てられていたはずのシューズが、ケニアで息を吹き返して、こんな姿になるまで愛用してもらえた。日本の方々の支援が、間違いなく現地の子どもたちの励みになっていることを実感しました。同時にこの現況を日本の子どもたちにもきちんと伝えないといけない、そしてものを大事に使うことを伝えたい――私は仲介役の義務としてその使命を果たさなきゃいけないと思ったのです。

ちなみにシューズを提供してくれた日本の子どもたちには、ケニアの子どもたちが育てて採取したひまわりの種をお礼として配ります。それを植えて緑化運動をしてもらうというのが目的なのですが、咲いたひまわりを見て、自分たちがケニアの子どもたちと繋がっていることを忘れないようにしてほしいなと。お互いが学ぶことの多かった2年目でしたね。
3年目、スラムでは陸上クラブが立ち上がっていました。部員が30~40名もいます。そもそも、ケニアでマラソン大会をやりませんかという誘いが当プロジェクトのきっかけとお話ししましたが、その『ソトコト マラソン』も例年開催されています。世界記録保持者クラスも出場したような大きな大会なのですが、ジュニアの部もあって、スラムからも、靴を送った何人かを連れていきます。ほとんどの子が初めてスラムの外に出て、思い切り走ることで、走る楽しさを覚え、もっと走りたいという夢や希望や持つようになりました。そんな思いを共有した子どもたちがクラブを発足していたんですよ。
DOWELL編集部: モーリス君ひとりだけだったのが、2年経ってクラブができるほどになったとは。でもスラムの劣悪な環境は変わりませんよね。
高橋さん: それがですね、今まで伏し目がちに生きてきた子どもたちがシューズを履いて、目をキラキラさせながら走る姿を見ていた親の意識が変わったんです。「子どもたちがもっとのびのび走れるように道をきれいにしたい。ゴミを掃除する方法を教えてくれないか」と相談にきたんです。

DOWELL編集部: 意識が変わったのは素晴らしいですね。でも、掃除のやり方から、ですか?
高橋さん: 今まで掃除したことがなかったんですよ(苦笑)。では掃除を一緒にしましょうということになり、最初は100名ほどの大人が集まったのですが、時間を追うごとに増えていきました。少しずつ道がきれいになっていく様子を不思議そうに眺めていた子どもたちも加わって、その日は暮れるまでみんなでお掃除したんです。
4年目になるとトレーニングの成果が出てきて、『ソトコト マラソン』ジュニアの部で、2、4、7番とスラムの子どもが入賞しました。ナイロビから来たきれいなシューズを履いたエリート選手たちに混じってです。表彰台に上った姿が地元のメディアなどで取り上げられ情報が広まっていくと、陸上をしていない子どもたちも、スラムにいる自分たちでも何かできるかもしれないと目標を探し始めたのです。シューズは最初こそ命を守る防具だったけれど、気づけば子どもたちに夢を与えて励ます存在になっていました。地元の大人たちも併せて変わっていき、子どもたちの夢をサポートするようになったのも大きな進化だと思います。
(※注)「JICA」https://www.jica.go.jp/index.html
いいことをして、この世界をよくしていこう。~ DOWELL(ドゥーウェル)~
www.dowellmag.com