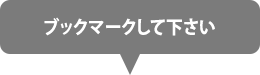アフリカ・ケニアなどの途上国の子どもたちへシューズを贈る『スマイル アフリカ プロジェクト』。シドニー五輪女子マラソンの金メダリスト・高橋尚子さんが11年にわたって尽力されてきたこのプロジェクトも、2020年3月で、いったん休止を迎えました。そこで、高橋さんのプロジェクトへの思いと現在の気持ち、そしてご自身が取組まれてきたさまざまな活動について、お話を伺いました。

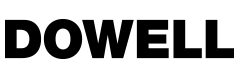

アフリカ・ケニアなどの途上国の子どもたちへシューズを贈る『スマイル アフリカ プロジェクト』。シドニー五輪女子マラソンの金メダリスト・高橋尚子さんが11年にわたって尽力されてきたこのプロジェクトも、2020年3月で、いったん休止を迎えました。そこで、高橋さんのプロジェクトへの思いと現在の気持ち、そしてご自身が取組まれてきたさまざまな活動について、お話を伺いました。
DOWELL編集部: 『スマイル アフリカ プロジェクト』は、11年目の昨年11月に通算で10万293足のシューズが集まり、目標としていた10万足をクリア。プロジェクトは大成功のうちに一時休止となりましたが、どのような気持ちになりましたか?
高橋さん: 正直嬉しいというより寂しいという感じですね。当初から10万足という明確な数字を掲げていたのではありません。実は一度でも使用したシューズは廃棄物扱いになってしまうのですが、こうした廃棄物を持ち込む規制が厳しくなって、続けていくことが困難になっていきました。息切れしてフェードアウトするよりは、どこかでちゃんと区切りをつけようとして設定したのが10万足。ピリオドをいったん打って、次のステップを考えようと話し合いました。
ただ11年間、続けてきてよかったと確信しています。またモーリスのことになりますが、数年目に彼はこんな話をしてくれました。
「ナオコは1年に1回しか来られないけれど、僕はシューズをもらって考え方も過ごし方も変わったよ。ナオコがいない364日は、僕が夢を持つことの大切さや走ることの楽しさをスラムの子どもたちに伝えていくから」と。その言葉を聞いたとき、もしこのプロジェクトが終わったとしても、現地の子どもたちの意識の中に夢や希望を根付けることができたかもしれないと思いました。
なかなかうまくいかないもので、モーリスは家庭の事情に不運も重なり、才能がありながら陸上選手になることは叶いませんでした。そんな彼の父親が亡くなり遠くの学校に引き取られたときも「僕はお父さんお母さんと一緒にいられなくなったけど、それでも走ることはやめていないよ。僕がもらったシューズには多くの日本の人たちからの頑張れという思いが込められているんだ。だから僕はこのシューズを履いて、多くの友達をつくって走ることを続けていくよ」という言葉が脳裏に焼き付いています。


DOWELL編集部: これだけ感謝してもらったら、日本の子どもたちも幸せですね。
高橋さん: 提供してきた日本の子どもたちにも感動させられたことがあります。ずっとシューズを提供してくれていた岩手県の中学校が東日本大震災に遭ってしまい、すぐにみんなを励まし少しでも笑顔になって欲しいとスポーツ支援に駆け付けました。
そのときに生徒会長が「私たちは地震を境に、提供する側から提供される側になってしまいました。でも私たちは震災の直後から靴はもらえたから、靴なしで過ごしたことはありません。今の私たちに靴を提供できる余裕はありませんが、災害がなくても、同じ年代の子どもたちが靴を履けない状況にあることを僕たちは知っています。だからこれから先、元の生活に戻りつつあるときには、必ず僕たちはまた靴を提供したいと思います」と話してくれて、お互いが遠くの人を思いやれていることを知って、とても嬉しかったですね。
DOWELL編集部: 子供たちの経験は何にも代えられませんね。このプロジェクトが世界と社会をよくする活動のサイクルであることを、感じたのではないでしょうか。
DOWELL編集部: 『スマイル アフリカ プロジェクト』は一時休止しましたが、高橋さんはJICAのオフィシャルサポーターもされていて、世界各地へ出かけられているのですよね。
高橋さん: 2011年にお引き受けした後、十数カ国に赴きました。やはりスポーツ関係のプログラムが中心ですね。ほとんどの途上国や貧困地域ではスポーツより勉学に重きを置いていることが多く、その結果、子どもたちの体力は著しく低いです。また規範を守れなかったり、同じことを辛抱強く反復することが苦手な子どもも多い。体力の増強や運動神経、反射神経の向上はもちろんですが、「ルールを守る」「秩序を守る」「他人との共存を考える」といったことを、スポーツを通して学べるように取組んでいるんですよ。
DOWELL編集部: 特に印象に残っている国はありますか?
高橋さん: 中米のエルサルバトルですね。治安がとても悪くて外を歩く人をほとんど見かけない国なのですが、卓球のナショナルチームと一緒にトレーニングの指導をするという機会をいただいたんです。チームは翌年に東京で開催された『世界卓球 2014』に初出場を果たし、日本で再会することができました。
そのときにある選手が目を輝かしながら、「日本はすごい。街が人であふれている。子どもがひとりで歩いたり、バスに乗ったりしている。女性がひとりでジョギングしている。こんなの見たことがないです。自分の国もそうなれるようにしたい」と言ったんです。
国を背負っているスポーツ選手は母国に帰ると、地元のヒーローであり、ヒロイン。そういう人たちが国の将来について夢や希望を語ることは、影響力が大きいと思います。スポーツの持つ力の大きさを、改めて認識できましたね。来年に延期になりましたが、東京オリンピック・パラリンピックが無事に開催されて、世界中から集まった選手が、同じような思いを抱いてくれることを願うばかりです。

DOWELL編集部: JICAの活動を通して、高橋さん自身が学ばれたことはありますか?
高橋さん: そうですね。JICAの現場では海外青年協力隊のスタッフと連動することが多く、彼らともよく話すのですが、まず現地の人たちに決して自分のスタンスを押しつけないこと。コミュニケーションをしっかり取って現地の人たちのことを知り、彼らの足並みに合わせて、一歩ずつ進むことが大切。そうすれば、国境、性別、年齢、障がい、経済格差といった壁を飛び越えることができると信じています。私が学んできたことであり、志を同じくする人たちに伝えていきたいことですね。
DOWELL編集部: 今までお話を伺ってきて、『スマイル アフリカ プロジェクト』は、まさに私たちが唱える「Do well by doing good.」を具現化しているものだと感じました。それでは最後に、高橋さんがこれから取組もうとしている「Do well by doing good.」活動があれば、お聞かせください。
高橋さん: 今度は何をやりましょうか(笑)。私のベースは走ること。「楽しい」「健康になる」「走る女性は美しい」といった魅力を伝えていくことが、私にできることです。現役の頃は、日本ではマラソンは観るものでやるものではなく、苦しく辛そうに走る選手をテレビの前で応援するというものでした。でも同時期にニューヨークのセントラルパークでは、市民ランナーたちが楽しそうに走っていました。その姿を見て、日本もこうなればいいなと思ってランニングは楽しいと発言してきました。、まさに今は皇居がセントラルパークとなり、走ることを楽しむ文化が定着しました。願って努力すれば叶うんですよね。
新しい取組みとして、2018年からベトナムでスタートした『オレンジマラソン』も応援しています。今も残る枯葉剤の影響を知ってもらうためのチャリティーマラソンで、参加費の一部が被害者救済基金に充てられるというものです。ちなみにオレンジは果物が豊かなベトナムでやるマラソンという意味と、枯葉剤を英語で「AGENT ORANGE=オレンジ剤」と記すことをかけているんですよ。
このようにずっと走ることの魅力を発信し続けて、世界に夢と希望、そして笑顔が溢れるようになればいいなと思います。それが私の「Do well by doing good.」ですね。

いいことをして、この世界をよくしていこう。~ DOWELL(ドゥーウェル)~
www.dowellmag.com